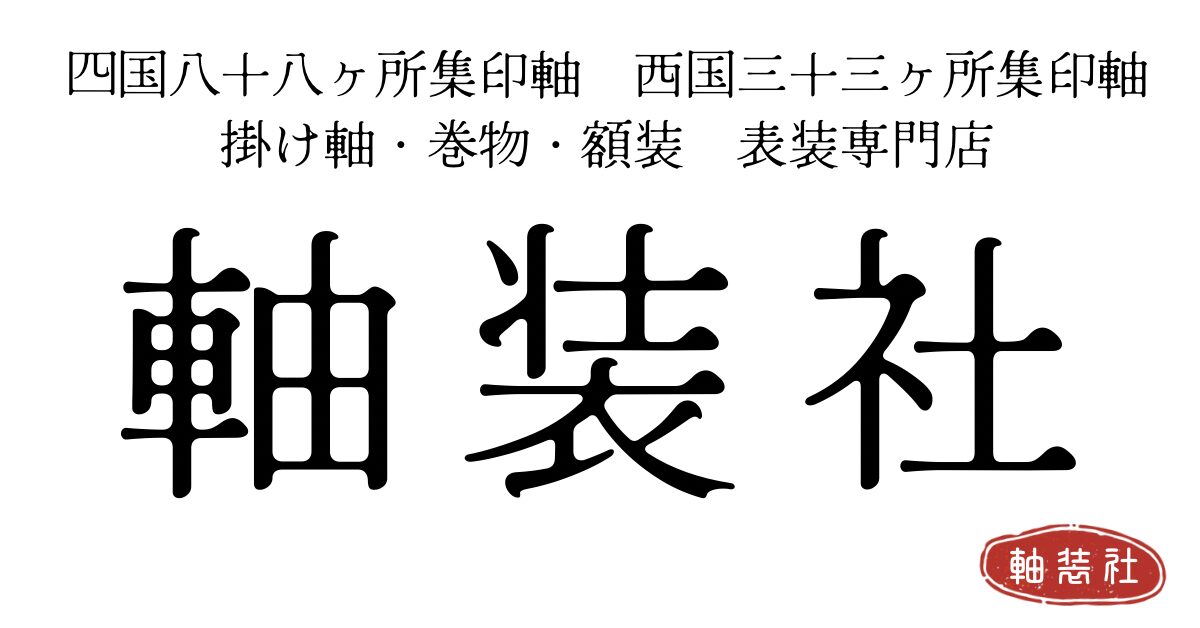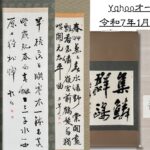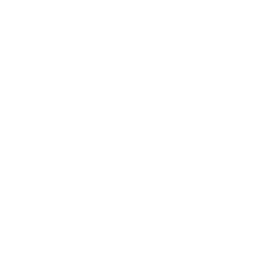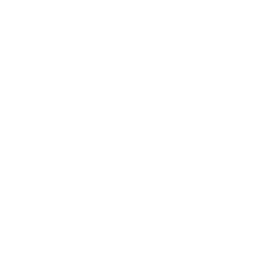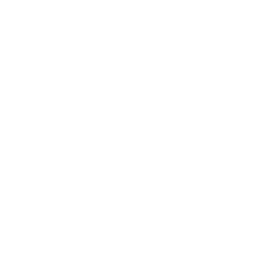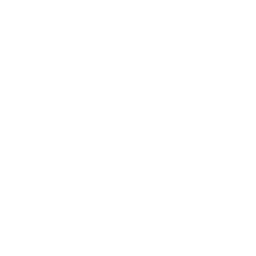涅槃像の歴史と仏教における重要性
涅槃像は、仏教における深い教義や信仰の表現であり、その歴史は数世代にわたって発展してきました。この像は、仏が涅槃に入る際の姿を象徴しており、多くの信者にとっては、悟りを指し示す重要なシンボルとなっています。本記事では、涅槃像の起源や歴史的な変遷を辿りながら、その背後にある仏教の教義についても掘り下げていきます。また、涅槃像が信者に与える影響や、どのようにして仏教徒の精神生活を豊かにしているのかを考察します。涅槃像の理解を深めることで、仏教思想の本質やその重要性を再認識し、自らの信仰や精神的探求に役立てることができるでしょう。興味深い歴史と豊かな象徴性が凝縮された本記事を通じて、皆様が新たな視点を得られることを願っています。
涅槃像の歴史

涅槃像(ねはんぞう)とは、仏教の開祖である釈迦が亡くなった姿を描いた絵や彫像で、寝釈迦とも呼ばれます。涅槃(ねはん)とは、サンスクリット語のニルバーナという言葉を音訳して涅槃といい、意味は「煩悩の火が消えた状態」をいいます。死にいたりて、完全に煩悩が消え、悟りが完遂するという事になります。ですから、死=悲しみだけではない、真の平穏でもある。そこから仏教では亡くなる事を「涅槃」といいます。
涅槃像の起源
涅槃像の起源は、釈迦の死後の信仰から始まります。釈迦が入滅する際の姿を模した像は、多くの地域で製作されましたが、特にインドにおいてその制作が初期の段階で盛んに行われました。古代インドの文献には、釈迦が安らぎと平和を持つ姿で横たわる描写が記録されています。これが後に涅槃像として具現化されていく基盤となりました。涅槃像は、釈迦の教えや生涯を讃えるために制作され、また信者たちに涅槃の概念を視覚的に伝える役割を果たしました。

このようにして涅槃像は、時代と共に形を変えながらも、釈迦の入滅を象徴する重要な宗教的アートとして位置づけられました。具体的には、インドの初期の作品には、シンプルなデザインや表情の乏しいものが多いですが、時が経つにつれて、装飾が豊かになり、より人間らしい表現が加わっていきました。
歴史的な変遷
歴史的には、涅槃像はインド国内だけでなく、仏教が広がる中で、さまざまな文化との接触を経てその形が変化してきました。

例えば、タイやミャンマーに見られる涅槃像は、地域の伝統と融合し、非常に華やかで装飾的なものが多く存在します。これに対し、日本では、平安時代に流行した阿弥陀如来の影響を受け、よりシンプルで静謐な表現を持つ涅槃像が制作されるようになりました。このように、地域によって異なるスタイルの涅槃像が存在することは、仏教の柔軟さと連続性を示す大変興味深い現象です。
日本では、涅槃会(ねはんえ)というお釈迦さまを尊ぶ仏教行事の際に拝観されます。日本では平安時代から製作され、高野山金剛峯寺所蔵品は最古の作例として知られています。
涅槃図から見る仏教への教義
仏教において、「涅槃」は生と死を超えた存在として理解され、苦しみからの解放を表しています。ブッダが確立した四聖諦や八正道は、信者がどのようにして涅槃に至るかを示しており、涅槃図はその教義の具体的な可視化とも言えます。涅槃図を見ることで、信者は仏教の教学を再確認することができます。

涅槃図の見方


お釈迦様の命日(入滅の日)は2月15日のため、十五夜の美しい満月が描かれています。
阿那律尊者(あなりつそんじゃ)の先導で天女達に付き添われてお釈迦様の生母・摩耶夫人が息子のもとへ向かっている場面です。摩耶夫人はお釈迦様の生後7日目に亡くなったと伝えられています。摩耶夫人は、今まさに涅槃に入ろうとしているお釈迦様に長寿の薬を与え、もっと多くの人にその教えを説いてほしいという願いでやってきたのです。
お釈迦様の枕元の木に描かれている赤い袋が、摩耶夫人がお釈迦様のために投じた薬袋です。「投薬」という言葉は、この故事によるものだと言われています。しかし、この薬袋は、摩耶夫人の願いもむなしくお釈迦様に届く前に木に引っかかってしまいました。この薬袋は様々な説があり、薬袋ではなく僧の持ち物で最低限許された袈裟と器が入った袋だという説もあります。神社によって解釈が違うのも興味深いですね。
お釈迦様が横たわっている宝座の周りには8本の沙羅双樹の木があります。向かって右側の4本は白く枯れていますが、これはお釈迦様が入滅したことを植物も悲しんだことを示しています。一方で左側の4本は青々として花も咲かせていますが、お釈迦様が入滅してもその教えは枯れることなく連綿と受け継がれていくことを示しています。


お釈迦様の周りを見てみよう



「頭北面西(ずほくめんせい)」で横たわり、今日でも亡くなった方を北枕か西枕で安置するのはこの故事からきています。
また涅槃像には、目が閉じているものと、目が開いているものがあり、目を閉じた涅槃像は、既に入滅した姿で、目が開いている涅槃像は最後の説法をしている姿を顕しているといわれるそうです。


お釈迦様の十大弟子。多聞第一「阿難陀(あなんだ、あーなんだ)」悲しみと喪失で気を失っています。美形で女難に遭いながらも真面目に修行を環椎したそうです。いかに阿難陀を美形に書けるかが、画家の腕の見せ所だそうです。
そんな阿難陀を心配そうに見ているのは天眼第一「阿泥樓駄尊者(あぬるだそんじゃ)」。気を失った阿難陀に清冷の水を顔に注ぎ助け起こしたそうです。この阿泥樓駄尊者は摩耶夫人を先導した阿那律尊者と同一人物だと言われています。
一枚の絵に時間軸の違いが生じています。
お釈迦様の足を触る老婆は何者か。これにはいくつか所説があるようです。お釈迦様が苦行を終え、下山したときにミルク粥を施した「スジャータ(難陀婆羅(なんだばら)」だという説もあります。しかしスジャータは少女のはずです。一般的な定説では「スバッダラ(須跋陀羅)」という120歳の老女だと言われています。その時の定説によって描かれ方が違うようで、作者の意図が大きく反映されていますが、どの時代の涅槃図にも総じて「阿難陀」とこの「老女」が描かれており、重要な女性であることは間違いないようです。




八部衆・夜叉。お釈迦様に教化され,仏法を守護する異教の諸神,八種の鬼神です。 普通は天,竜,夜叉,乾闥婆 (けんだつば) ,阿修羅,迦楼羅 (かるら) ,緊那羅 (きんなら) ,摩ご羅伽 (まごらか) の一群の像を呼びます。


涅槃図の下の方には、50種程の動物たちが描かれています。その中には、像など当時の日本では見ることができなかった動物や想像上の生き物の姿もあります。食物連鎖の理や、普段は争い合う諸動物も、揃ってお釈迦様の入滅を悲しんでいます。ちなみに50種くらいの動物の中に、猫がいない理由は「ネズミはお釈迦様の使い」とされていることに由来するそうです。ちなみに涅槃図の見方で今回参考にさせていただいたお寺には猫の絵があるそうです。
信者への影響と象徴性
涅槃像は多くの仏教徒にとって、精神的支えや道徳的指針とされています。信者は涅槃像を通じて、ブッダの教えを反映し、彼の生き様や解脱の境地を思い起こします。このような像は、信者にとっての尊敬や感謝の象徴でもありますし、苦しみを癒やす一つの触媒としての役割も担います。しかしながら、像がある場所は限られています。毎年2月15日はお釈迦様の命日(旧暦)として、全国で釈尊涅槃会が行われています。釈尊涅槃会とは仏教の開祖であるお釈迦様が亡くなられた日に行われる法要です。お釈迦様の教えや徳に感謝し、遺徳を偲ぶ追悼報恩の法要として知られています。そして、多くの寺院ではお釈迦様の涅槃(亡くなられた)時の様子を模している「涅槃図」の軸が飾られ、お釈迦様の教えを今日に伝えています。


こちらの涅槃図は令和7年4月のオークションで出品予定です。