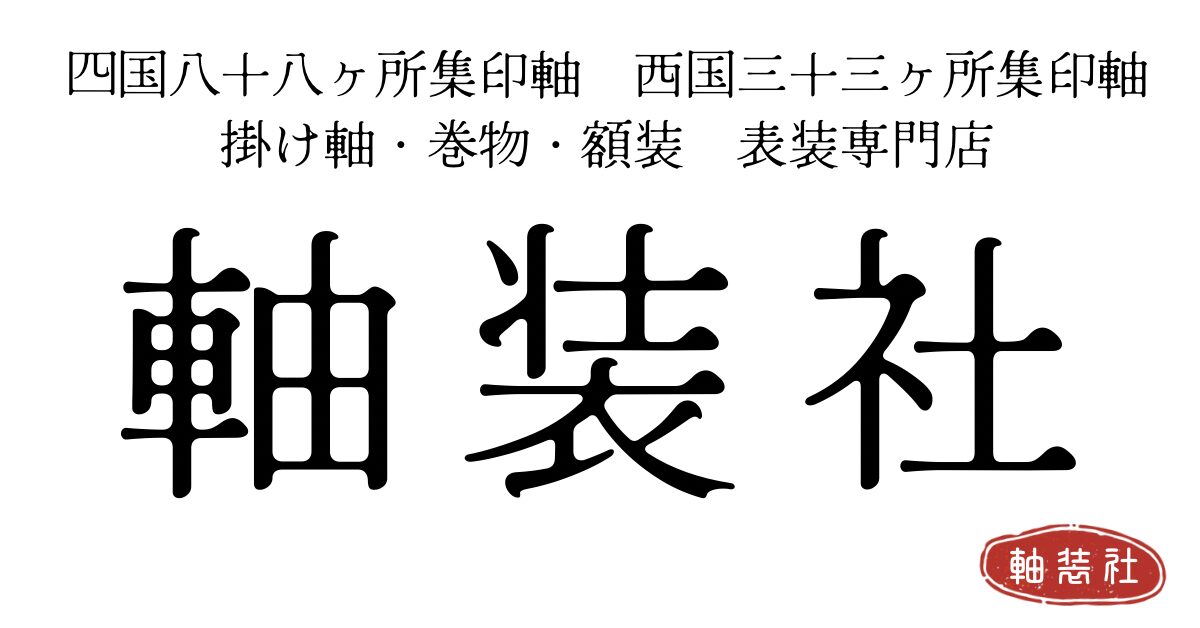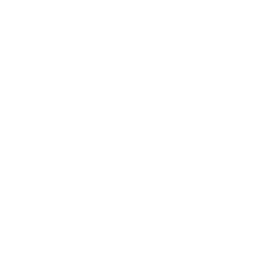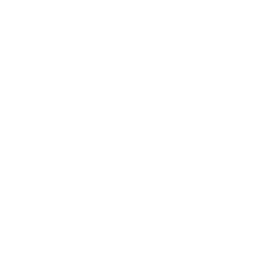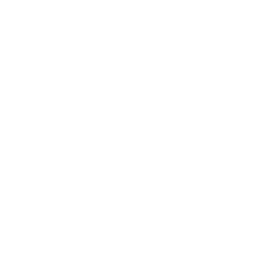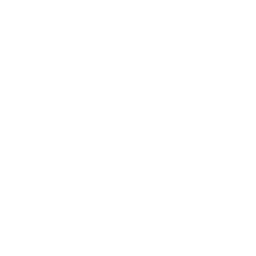傷みすぎ紙本!三輪田米山を修復!

愛媛県松山市の軸装社の近くには「日尾八幡神社」があり、幼少期はよくお祭りや初詣にも行っていました。その土地の子供だったので学校行事でもよく訪れていました。子供が生まれお宮参りにはもちろん訪れ、その子供が成長し剣道を習い、初めての試合も日尾八幡神社のお祭りの試合。『縁がある』とはこの事でしょう。そこの神主さんの書を修復するのは2枚目です。そしてだいたい米山の物はボロボロです。今回も気合を入れて修復しました。
べいざんとは

べいざん(みわだ べいざん)は、書道家で近代書の先駆とされる三輪田米山(1821~1908)のことで、豪気大胆で天衣無縫な書風で知られています。
三輪田米山は伊予松山の日尾八幡神社の長男として生まれ、神職として過ごしました。王羲之や趙孟頫、細井広沢などの書法を学び、法帖を庄屋から借りて必死に学んだと言われています。60歳を迎える頃にはこれらの書法に縛られることなく、誰の書とも違う個性的で破格の書風を確立しました。
三輪田米山の書は、肉筆は入手しにくいですが、拓本は肉筆に迫るものがあります。また、三輪田米山の日記には「酒を飲まぬと、筆をとること難し」とあり、酒に酔って理性や常識を捨てて書くことで創作のインスピレーションを得ていたのかもしれません。(GoogleAIより)
ボロボロ紙本

社長がオークションで入手してきた古い紙本や絹本、またはボロボロの軸や色紙。それらを修復する日々を過ごす中、親しみを覚えた三輪田米山。その米山がぐしゃぐしゃで、でもよくぞ残っていてくれたという、笑いと悲しみと安堵でいっぱいになりながら全体を確認します。上が裂けてなくなっており、両サイドはボロボロです。絵にかいたようなぼろ具合です。

頭と両サイドが部分的にない。色が似た画仙紙を貼って一枚物に見せかけた後裏打ちをする。①米山②画仙紙③裏打ち紙の3枚構造を思い描いていましたが、ベテラン職人に「そんな古く黄ばんだ画仙紙はない」とあっさり却下されました。

今回はひどい染みもないので「洗い」はなし。とりあえず整えるかと、刷毛を用意します。
整える


敷紙を引き、酷く傷んでいる場所以外を軽く水で湿らせたら刷毛で伸ばします。
ひどく傷んだ部分は水浸しにします。千枚通しやピンセットを使い細かいシワを広げます。指を使うと紙の繊維が傷み破れたり溶けたりします。水浸しにした部分に空気が入り浮いてしまう部分も丁寧に空気を出します。

ただし、水浸しにしたら、紙本はもう持ち上げる事ができません。溶けるか破れるかしますので、水を大量に使ったらその後のシワを伸ばす作業は、「水の移動する力」を利用して「水分を取る」という行為を行いながら伸ばしていきます。

二つに裂けていた部分を慎重に合わせて、何度か調整を行います。
紙はわりとまっすぐではないです。破ける際に加わる力や繊維などで僅かに歪んでしまい、何度調整しても隙間が空いてしまう所が出てきます。
ベテラン職人さんの曰く、「修復とは自分との闘い」だそうです。このくらいでいいか、という心は作品に反映されます。せっかくの米山なんで、ここで諦めたくありません。頭はないし、横もなくてボロボロだけど、できる限り修復したいと思いました。
リスクを覚悟で指を使い、そこそこ無理やりくっ付けました。
指を使うと繊維が寄れてしまいます。寄れるとは、大げさに言えば穴をあけちゃうと言うことです。作業を行うのは作品の裏側なんで、どのくらいのダメージかは乾いた表面を見ないと分かりません。なんせリスキーです。
これは紙本がちょっと黄ばんでいるし、裏打紙も似たようなベージュを使うつもりだったので分からないかもしれない。ただ白の画仙紙はすごく目立つので、いまだかつて綺麗に修復できたことがないように思います。

全体が整ったら、裏打ちを行います。裏打ちはベテラン職人さんに相談し、ベージュと白の2枚貼りで色を合わせてみました。乾かすために仮張りに張り付け一晩置きます。頭がない部分は裏打ち紙の色で綺麗に誤魔化せたらいいな・・・でもこればっかりは乾いてみないと分かりません。この段階では紙本と裏打紙の違いがよくわかります。私は裂けた部分を綺麗に合わせる事がでたのでもうこの時点で達成感がありました。



乾燥

乾いた米山、完璧じゃないですか。
これには社長もご満悦いただけました。ベテラン職人さんも「まぐれが当たったな」とまんざらでもない笑顔でした。まぐれじゃなく、経験値が物を言うんだなと毎回感じます。ここまで綺麗に裏打ち用紙だけで色を合わせてくるなんて、私はあと何年経験すればできるんだろう・・・。色合わせに関しても、素晴らしい感性を持っているベテラン職人さんです。彼が健在のうちに様々な事を吸収して、次世代に引き継げるよう邁進してまいります。
ちなみに、この後は「折止め」を入れ、プレスしてから軸にすべく「裂取」「付け回し」「耳折り」「総裏」「仕上げ」が行われます。私は「折止め」まで作業を行ったら後は社長に回し、「仕上げ」の段階で手元に帰ってきます。「仕上げ」は私が行います。最初と最後の作業に携われるわけです。



令和6年の年末はこのままで、令和7年に入り、社長が「裂取」を行うのが楽しみです。完成すればまた写真に収め、記録を残しオークションへ出します。作品一つ一つで修復に違いがあります。紙本が思ったより薄かったとか、化学糊を使用した裏打紙がうまく剥げなくて本紙の層まで剥いでしまったとか、剥ぐという作業の段階でも様々なトラブルに見舞われます。一つ一つに思い出があり、写真を見返す事で思い出し次の予習復習に活かす事ができます。また懲りずに次の修復を記録し、成功も失敗もブログでお伝えできればと思います。