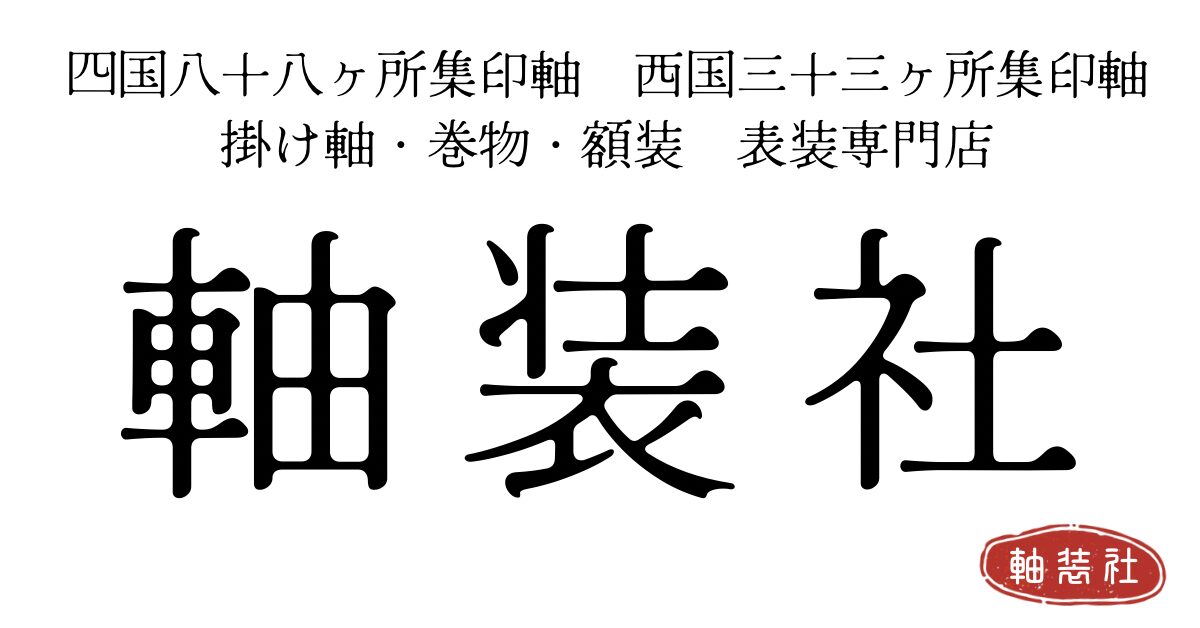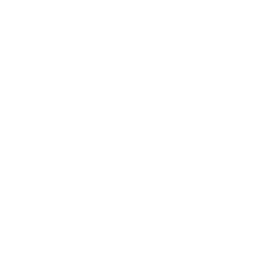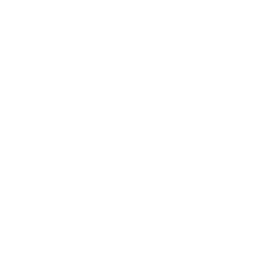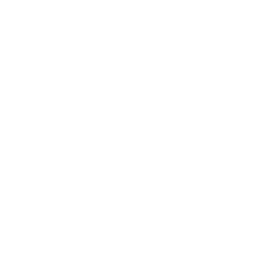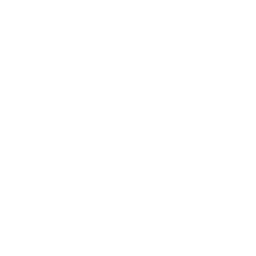【修復】 中村梧竹の書を洗う

中村梧竹とは
詩人・書家の名前です。
中林梧竹(1827~1913)は、肥前国(佐賀県)小城鍋島藩士の出身で、明治三筆の一人に数えられています。山内香雪に師事し、清国では潘存に師事しました。六朝の碑版法帖を多く持ち帰ったことで知られています。中林梧竹の書は、独特の筆致で愛好者が多く、富士山頂の銅碑「鎮国之山」や、千葉県成田市成田山新勝寺境内の「集王聖教序・般若心経」の臨書碑などが有名です。(AIによる概要)
よく修復で見かける中村梧竹先生の書を修復。古い紙本だとすでに傷んでいるので扱いはより慎重に、ていねいに、デメリットを考えながら作業を行います。私はこの柔らかい紙本が苦手中の苦手。いっそ破れてボロボロの方が好きだったりしますが、何事も経験ですね。
観察

痛みがひどく、染みもひどかったです。染みは「過マンガン酸」で着け置きし、しばらくしたら「しゅう酸」で流します。書での染み抜きはこのセットをよく使います。ただしどちらの薬剤も原液を薄めて使いますが、濃ければ濃いほど紙本も傷みます。この絶妙な加減は私にはまだまだ経験が足りません。でもとりあえず洗ってみました。

裏を剥ぐ

本来は裏を剥いで紙本一枚のみで洗いますが、今回保険をかけて裏を剥ぐ前に洗いました。なんとか綺麗に洗い終わり、一日乾かし、翌日裏を剥ぐ作業に取り掛かります。裏打ちですが、昔は紙がなく、貴重だったので継ぎ接ぎで行う事が多かったそうです。昔の職人さんはとても綺麗に継ぎ接ぎを行っており、1部(3mm)だけ重ねています。歪みもシワもなく、機械ではなく手打ちでびしっと揃っていて、職人技を感じます。

剥ぐ作業は慎重に行います。繊維の向きや引っ張る方向などを考えながら、裂けたら逆方向からまた剥ぎ、いろいろな方向からなるべく破らないように剥ぎます。




整える

少し乾いてくると、指で持ち上げて動かせるようになってきます。刷毛を使い伸ばしていきます。書で多い半切は縦の長さが134㎝くらいあります。ちょうど中間を起点に、そこから伸ばしていきます。刷毛で伸びきらない部分は水の力で伸ばしていきます。皺ものび、裂け目もある程度はくっつきます。




裏打ち

裏打ちを行い、仮張り板に張ります。裏打ちは刷毛と糊を使い、手で打っていきます。機械打ちと手打ちの違いはいろいろな面でメリットデメリットがあります。修復後の紙本においては手打ちの方がメリットが大きいです。今回は伝統的なでんぷん糊を使います。糊の濃さは調整が必要ですが職人世界の「見て覚える」文化がまだ根強いため配合割合などの数字はわかりません。見て触って覚えます。

折り止め

乾いたら折り止めを入れます。紙筒を軸棒と見立てて、筒に巻いていきます。裏面に折れの後がついていてば、そこを補強します。1部(3mm)の薄さに切った裏打ち紙をでんぷん糊で貼っていきます。裏打ち紙が太すぎたり、無暗に折り止めを入れたりすると更なる折れを発生させます。そこを調整しながら折り止めを入れていきます。

修復を終えて

修復の後は、裂の付け回し等が行われ、総裏を行い、その後私の元へ帰ってきて仕上げを行います。
上下の軸棒と表目を取り付け、カンを打ち、紐を取り付けたら完成です。
染みだらけでボロボロだった作品はどこの部屋に飾っても恥ずかしくない美しい丸表具の掛軸に完成です。今日もありがとうございました。